

新たな行動指針策定のために、
討論や提案を行ったプロジェクトメンバー。
その当時の様子についてお話しいただきました。
-

日本電子専門学校 校長 船山 世界 -

学校法人電子学園 総務部長 大桃 洋 -

総務部 松島 果穂 -

総務部 出谷 聖也 -
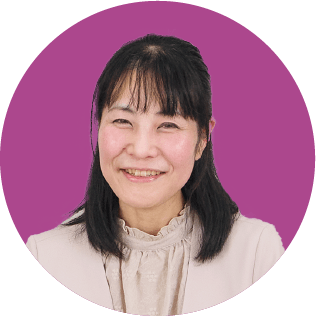
総務部 河島 綾 -
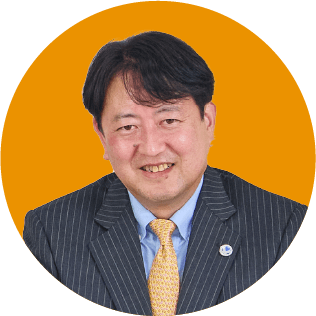
日本電子専門学校 人事部長 丸山 治
行動指針のはじまりは
4項目の「学生クレド」
船山:「ありがとう たちむかう」という新しい行動指針が策定されました。みなさんが参加した「行動指針推進プロジェクト」の成果ですが、実は行動指針の策定は2012年に端を発しています。
大桃:そうなのですね。プロジェクトの統括を総務部長が務めるということで、前任者から引き継ぎましたが、そもそもどのような経緯を辿って今に至っているか伺いたいです。
船山:当時、学生が入学しても卒業せずに退学してしまう、いわゆる「ドロップアウト」が大きな課題となっていました。これをどうにかして改善したいという思いから「ドロップアウト対策委員会」を設立。その頃は建学の精神こそあったものの、「NEXT10」や経営理念、行動規範が整備されていませんでした。
対策委員会で知恵を絞っていた頃、世間では「クレド」という言葉が注目を集めていました。「クレド」は、ラテン語で「信条」や「約束」を意味しますが企業活動の指針として導入する例が増えていました。
丸山:世界的なホテルチェーンのリッツ・カールトンがクレドを活用し、高いサービスレベルと顧客満足度を向上させたことで有名ですね。
船山:そうです。教職員研修会に、リッツ・カールトンホテルの支配人をお招きして、講演会を開催しました。対策委員会ではさまざまな取り組みをしましたが、その中の1つにリッツ・カールトンのような学生版のクレドを作るアイデアがあり、2013年に行動指針の原点とも言える「学生クレド」が完成したんです。
「学生クレド」はシンプルな4項目で、学生にとってわかりやすく、大切なことがまとめられました。学生に知ってもらい、退学せずに勉強を続けて欲しいと思ったんです。
「電子学園人」
それが集約された
行動指針


教員・職員に
「行動指針」の広がり
丸山:「学生クレド」が完成した後、背景にある理念を教員や職員にも広げる動きが生まれました。2016年からスタートする長期ビジョン「NEXT10」を検討する過程で、総務部と人事部が中心となり、教員向けの行動指針を策定する流れでした。
船山:「学生に実践させる前に、まずは教員が範を示すべき」という声が教員の間で上がり、それを受けて丸山さんが話した教員の行動指針が策定されました。
丸山:教員の行動指針は28項目に及ぶ具体的な内容でした。1年後に職員の行動指針10項目が完成します。
船山:現状の行動指針は2018年の4月からでしたね。教員の行動指針28項目に照らして、普段の教育活動でできたかどうかを教員自身が5段階で自己評価。行動指針を遵守できるように、半期に一度自己点検を行い、実践を振り返る仕組みとして定着しています。
丸山:職員の行動指針の作成にあたり、職員の意見を取り入れようと、職員一人ひとりから行動指針にしたい項目を提出してもらい、それを基に主任以上のメンバーで検討を重ねた結果、10項目が選ばれました。
出谷:そうでした。この「行動指針推進プロジェクト」ができる前に、「行動指針作成プロジェクト」がありました。私はメンバーではありませんでしたが、全職員に対して実施したアンケート調査の集計作業に協力しました。人材育成、コンプライアンス遵守、情報共有などに関し700項目を超える行動指針案を集計した記憶があります。
「行動指針作成プロジェクト」の後、「行動指針推進プロジェクト」が立ち上がりました。
丸山:そのタイミングで、出来上がった行動指針を周知・実践させる「行動指針推進プロジェクト」にバトンタッチして、私は一旦プロジェクトから外れました。
時を経て学園全体の
行動指針に
大桃:行動指針は人事考課の評価基準にもなっていますよね。
丸山:そうです。例えば、職員の行動指針の10項目のうち4項目が人事考課の項目になっています。人事考課に関することなので、改めて「行動指針推進プロジェクト」に参加することになり、メンバーのみなさんと一緒に活動してきました。
大桃:2018年に現在の行動指針が策定され、「行動指針推進プロジェクト」により一定の浸透が図れたのではないかと思います。一方、時代が急速に変化する中で「今ある行動指針を見直すことも検討して欲しい」と、役員から宿題をいただきました。
出谷:「行動指針作成プロジェクト」に関わり始めてから7年が経ちます。行動指針がどのような経緯で生まれ、どのように発展してきたのか、行動指針を巡る背景を改めて知ることができました。
松島:私にとっては、入職して最初に深く関わったのがこのプロジェクトでした。プロジェクトを通じて、自分自身が大きく成長できたと実感しています。メンバー間の意見交換や、ミーティングでの議論を通じて、問題解決に向けた考え方や進め方を学ぶ貴重な機会となりました。
河島:私も同じです。プロジェクトに参加してから、出谷さんや松島さんと事前に打ち合わせを行い、どうすればより有意義なミーティングにできるかを考えながら取り組んできました。
船山:行動指針は学生向けからスタートし、その後、教員や職員の行動指針が策定された。その時々の課題に取り組むプロジェクトメンバーや協力者がいて、拠り所となる行動指針が誕生しています。今回、iUと日本電子専門学校の教職員が一丸となった、学園全体の行動指針として新しく生まれ変わったことを大変嬉しく思います。


2022年が転換期
活動が
大きな
うねりとなる
推進メンバーの思いと
課題への挑戦
出谷:行動指針が策定され、これを教職員に認知してもらうために立ち上げられたのが「行動指針推進プロジェクト」です。しかし、教員と職員とでは行動指針の内容が異なり、さらに職員は各部署でさまざまな業務を担当しているため、一律の方法で推進するのは難しい。
私や松島さんがプロジェクトメンバーとして取り組む中で、特に課題となったのは、職員が「行動指針を自分の業務とどう結びつけるのか」を具体的にイメージしづらいという点でした。
松島:業務と行動指針がどのように結びつくかを考えるため、職員、後に教員も対象としてインタビューを実施しました。そして、その内容を学内で共有することで、行動指針を具体的に理解してもらい、実践のヒントにできればと考えました。それが、「行do指針推進通信」でインタビュー記事を取り上げるようになった理由です。
出谷:年8回ほどインタビュー記事を発行しましたね。
松島:はい、教職員一人にフォーカスして、担当している業務内容や、どのような気持ちで働いているかをインタビュー記事としてまとめました。
出谷:「行do指針推進通信」の発行は50号を超えました。この中でインタビュー記事は30本くらい掲載しています。
船山:本当に素晴らしい取り組みだと思います。教職員が自然に行動指針にふれる機会を増やし、その内容を意識するようになったことは大きな成果ですね。「行do指針推進通信」が50号も発行されているという事実に驚きます。